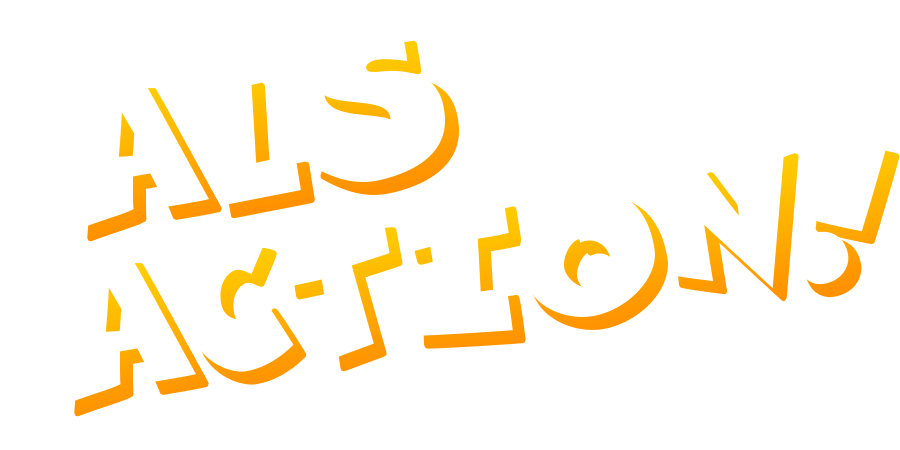2021.03.31
- 連載
- 患者さんメッセージ
ALSを受け入れられたとき
連載 患者さんメッセージ「Move Forward」vol.3

代表 竹田主子(医師)
- 目次
ALS発症から診断、そして療養生活に入った時のことについて
私は子育てと仕事の両立に必死だった42歳でALSを発症しました。子供は小学生と中学生でした。
ある日突然足が突っ張り、うまく歩けなくなりました。
その後はあっという間に手に力が入らなくなりました。私は料理が大好きでしたが、家族にご飯が作れなくなった時は泣きました。
約1年後に診断がついた時には覚悟はしていましたが、いざ告げられて真っ先に思ったのは「私、死ぬんだ…」ということです。当時は呼吸器を付けて生きるなんて思ってもいませんでしたから、診断してくれた医師に「私のALSのタイプは進行が早いですか?」と泣きながら尋ねました。その後はわらにもすがる思いで、遠方も含め、6ヵ所の病院に行き、専門家の話を聞きました。また日本ALS協会の方にお話を聞いたり、患者会に参加したりしました。でも発症したばかりの私は、呼吸器を付けた患者さんに会っても、正直ピンと来なくて、違う世界に迷いこんだ気がしていました。
家族に対しては、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。あっという間に言葉が不明瞭になり、食事も全介助になってしまいました。ただでさえ仕事で忙しい夫には介護や家事、福祉関係の対応で負担をかけてしまい、子どもたちにとっては頼れる母親から心配をかけてしまう存在になってしまいました。家庭もギスギスして来て、家族に迷惑をかけるくらいなら自分が死ぬべきだと思いました。元気だったらいろんなことができるのにと思いながら涙に暮れていると、それを非難され、「好きでこんな病気になったわけじゃない!」と悔しくて涙が止まりませんでした。「肺炎になっても、治療はいらないし、呼吸器をつけない。」とカルテに書いてもらったこともあります。
価値観の転換に至った経緯について
人生の途中で突然障がい者になるとショックを受けます。
今まで、普通に生活していたわけですから、どうしても、そのときの自分と比べて、自分が無力で価値のないものに思えます。
価値がないどころか、周りにとって厄介者になった気持ちになります。
どんどん身体が動かなくなるのは恐怖ですし、治らないとなると人生に絶望し死にたくなります。

心が前向きになるきっかけは、24時間介護認定が行政からおりて、家族に迷惑がかからなくなり、さらに、視線で入力できるパソコンを導入出来たおかげで、仕事や交遊関係などで、どんどん世界が広がり、自分に対する価値観が変わったことが大きかったと思います。
やがて、体は不自由になったけれど、自分全体の価値が下がった訳ではないと悟るようになります。
その段階まできたら障がい者である自分を受け入れられるようになり生きがいを見つけるようになります。
私は自分を受容するまでに4年かかりました。
しかし価値観が変化すると障害で失った価値以外にも、自分には多くの価値があること、障がい者による外見の変化より、親切さ、寛大さ、賢明さ、努力、協調性など内面的価値が人間としては大事であることに気付き、そして、他人または一般基準と比較するのではなく、自分自身の価値に目を向けるようになります。
つまり、障害が気にならなくなり、これが私! と思えるようになるのです。
これは私だけが考えたことではなく、第二次世界大戦で身体障がい者になった人たちの大規模調査でも、同様の心理状態が明らかになっています。今は自分が病気であることを忘れて、みなさんと同じ感覚で生活しています。むしろ病気になる前より、広く世の中に貢献したいという気持ちは強くなりました。
現在の生活、仕事
主に大学や医療者向けに講演を行ったり、執筆活動をしたりしています。
また毎年看護学生さんを最大10人受け入れて、ケアの方法を数ヵ月にわたって教えています。
自由な時間は仕事7割、SNSでおしゃべり2割、買い物1割という感じで過ごしています。
訪問看護や訪問リハビリ、入浴、トイレ、着替えなどで時間がかかるので、結構忙しく、あっという間に一日が終わります。
患者さん、ご家族や周囲の人々に必要なこと

ALSは家族内でなんとかなる病気ではありません。
呼吸器を付けるかどうかにかかわらず、とにかく情報を集めましょう。ALS協会に問い合わせると、地方の支部の患者会を紹介してもらえます。またFacebookでは ALSのグループがあり、発症から間もない患者さんが悩みを相談すると、先輩患者・家族から生活の工夫などを聞くことが出来ます。私は見ているだけでしたが、随分参考になりました。ALSは、24時間介護が必要な病気ではありますが、介護保険と重度訪問介護制度を使えばヘルパーさんに入ってもらえます。資産家しか生きていけないわけではありません。ヘルパーさんや訪問看護師さんなど、他人が家に長時間いる状態に最初は抵抗があると思いますが、それぞれのご家庭に合ったスタイルがきっと見つかるはずです。
またあえて良いところをあげると、だいたい何ヵ月後にこれが出来なくなるな、ということが分かるので、例えば福祉用具や、コミュニケーション方法、医療の問題を、人に相談したり、自分で調べたりして、十分に準備出来ます。
また、アタマは正常なので、パソコンがあれば、なんでもできますし、飛行機で海外や日本国内を飛び回って、仕事をしている人もたくさんいます。子育て孫育ても出来ます。良い子に育ちますよ。昔は天井を一日中見つめながら、何も周りに伝えることが出来ずに病院で死んでいく病気でしたが、今の時代、ALS患者は、無限に活動的になれるのです。
ご家族は患者本人から「死にたい」 という言葉を聞くかもしれません。
でも、「生きられるものなら生きたいけど」という気持ちが隠れています。
まずはヘルパーさんにできるだけ入ってもらうことと、ご本人が精神的に孤立しないように、生きがいを持って生きていけるように、環境を少しずつ整えていってください。
どうすれば自分が主体となって生活を回せるか、そして味方になってくれる人を増やすことができるのか、知恵を絞りに絞ることが鍵です。情報はできるだけ集め、同病の先輩のお話を聞くこともすごく大事です。でも、最終的には自分が考えないとダメです。
誰もなりたい自分になる答えは持っていないのです。一緒に頑張りましょうね。
新たな働きかけなど、検討していること
今老若男女問わず「死にたい」 という言葉がネット上で飛びかっています。
様々な事情があると思いますが、発言者が高齢者や神経難病患者、重度障がい者の場合は、その言葉をそのまま受け入れる人が多いのも事実です。
それは実情を知らない、自分には関係ない、考えたくない、役に立たない者はいなくなればいいと思っているなど、理由は様々だと思います。
でも誰もが心身が不自由になる可能性を持っています。
その時に、周りの人たちが「そう言ってることだし死んだ方がいいよ。」と安易に切り捨てるのではなく、救おうという方向に向かうように、社会全体の意識が変わるといいなと思っています。
これからも医療者を含め、社会に向けてALSの実情を発信し続けて行きたいと思っています。
メッセージ
絶望のどん底にいたとしても、人間は置かれた環境に適応できる驚異的な力を持っています。
その先に病気になる前よりも輝く人生が待っていることもあります。
それは打ちひしがれた患者さんの姿からは想像することは出来ません。
だからこそ、この病気になったから、この人は終わりだな。。という先入観を持つことなく患者が困っていることに寄り添って欲しいと思いますし、医療だけで手に負えないことも、様々な職種の協力を得たり、社会資源を使って支援ができるということを知っておいてほしいと思います。
本コンテンツの情報は公開時点(2021年3月31日)のものです。